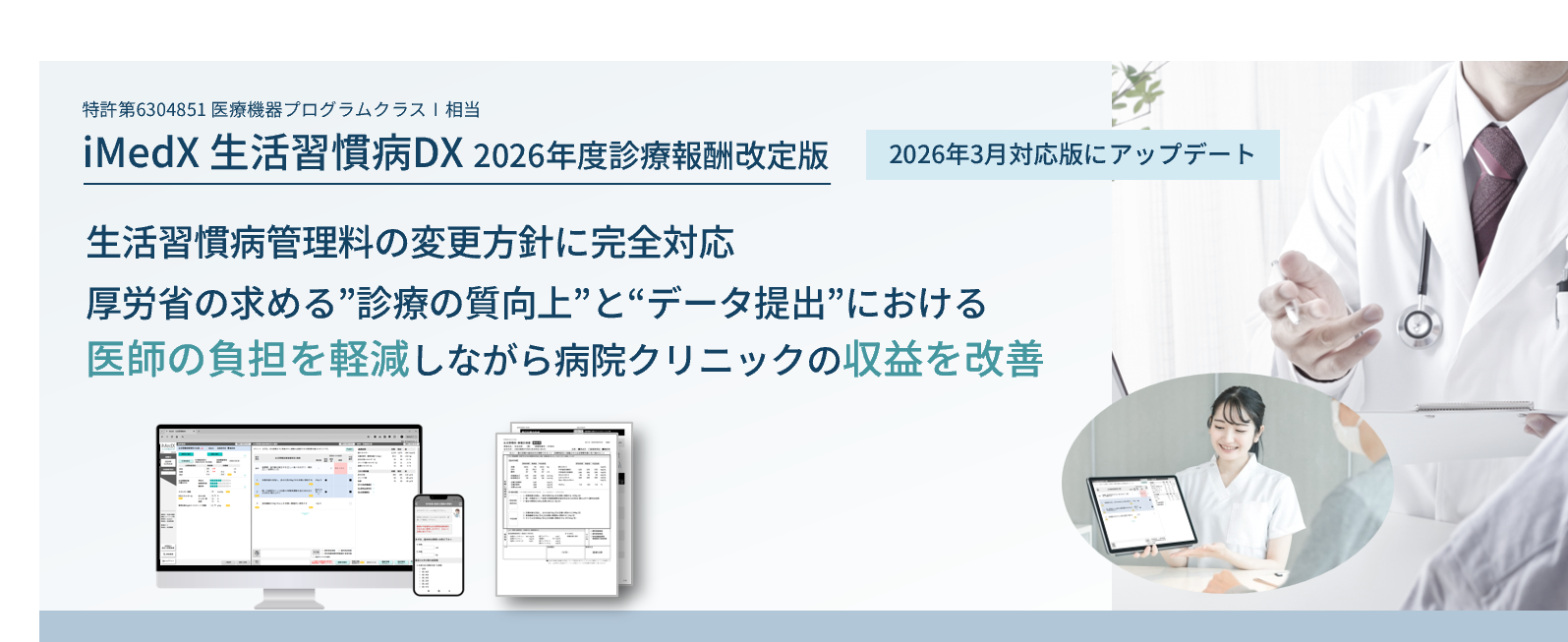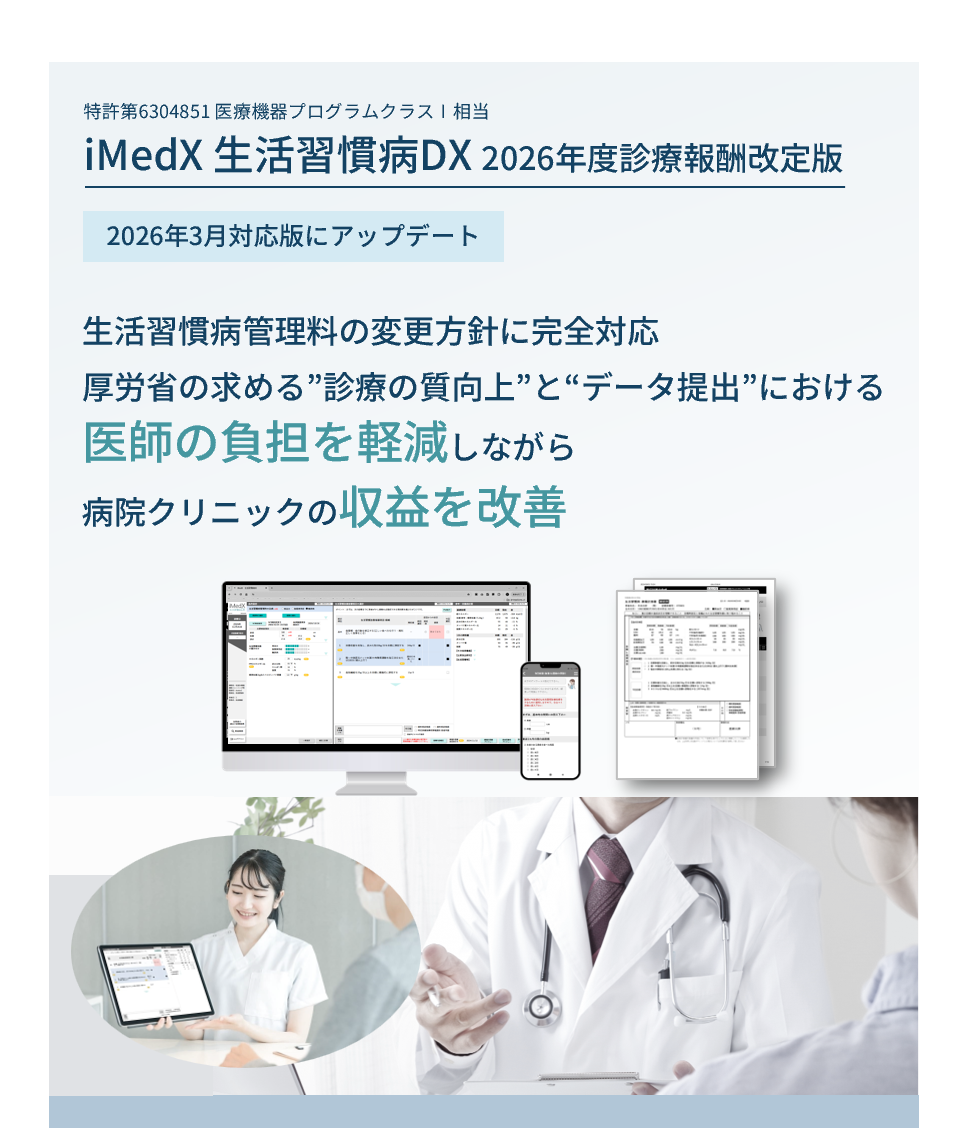【速報】令和8年度(2026年度)診療報酬改定での生活習慣病管理料の変更点と実務対応
2026年1月23日に公表された短冊(診療報酬改定の個別改定項目について)をもとに、生活習慣病管理料の見直しポイントを分かりやすく整理。あわせて改定の狙い、病院・クリニックへの影響、現場で今から準備すべき対応を解説します。
本記事は、厚生労働省が令和8年1月23日に公表した中医協総会資料(中医協 総-2)「個別改定項目について」に掲載された内容(いわゆる短冊)をもとに、令和8年度(2026年度)診療報酬改定における「生活習慣病管理料」の変更点を整理したものです。正式な点数・算定要件は、短冊に加えて通知・疑義解釈等で順次明確化されます。新たな情報が公表され次第、本記事は確定情報に合わせて速やかに更新します。
特に今回の改定において、多くの医療現場において最も影響が大きいものは、外来データ提出関連と思われます。外来患者に係る診療内容データ提出した医療機関のうち、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関を高く評価(加算等)をする方向が示されています。
本記事では、病院・クリニックの現場で「何が増えるのか」「何を先に決めるべきか」を、できるだけ実務目線で整理します。
1. 生活習慣病管理料:令和8年度
(2026年度)診療報酬改定の要点
外来データ提出と“質の評価”が最大の論点──診療の内容(実績)で点数が変わる方向へ。
本改定では、生活習慣病管理料に関して複数の見直しが示されています(例:療養計画書の署名不要化、眼科・歯科連携の加算新設、生活習慣病管理料(Ⅰ)における6か月に1度の検査必須化、糖尿病主病患者の「在宅自己注射指導管理」の扱い見直し など)。その中でも、現場負担と経営(算定・収益)への影響が大きいのは、「外来データ提出」と、それに紐づく“質の高い生活習慣病管理の実績評価”だと考えられます。
今回のポイントは、外来データを継続的かつ適切に提出できる体制を前提に、「生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から」評価体系(充実管理加算1〜3)が設計されている点です。つまり、評価の焦点が「やっているか」から、「ガイドラインに沿って適切に診療を実施できていることを実績データで示せるか」へ移りつつあります。機能強化加算にも外来データ提出の届出が望ましいとなりました。
外来データ提出関連以外の療養計画書の署名不要化や連携加算などは、現場の一部負担軽減や加点機会になり得るものの、収益上のインパクトや院内オペレーション全体を作り替える規模という意味では、外来データ提出と質の評価ほど大きくはなりにくいと見込まれます。
これにより、医療現場では当面、以下の対応が最も重要になると見込まれます。
なお現時点では、何をもって“質の高い実績”とするか(充実管理加算1〜3の具体的な評価基準)や、外来データ提出で求められる提出項目・様式の具体案が十分に示されていません。今後、通知・疑義解釈等で要件が具体化されるのを待ちつつ、確定情報が出次第、本記事も速やかに更新します。
また、外来データ提出の準備には最低でも4~6ヵ月かかり、また実績評価基準の中身によってはそれ以上の期間が必要となるため、医療機関経営の観点からは、可及的速やかに準備を開始する必要があります。
2. 今回の改定の背景と国が求める意図
国は「アウトカム評価」を通じて”診療の質”を担保する狙いがあると考えられます。
今回の改定の背景には、中医協の議論でも繰り返し示されてきた「データに基づく適切な評価」と「アウトカム評価の推進」という大きな方向性があります。入院領域ではデータ提出を前提にアウトカム評価を進める方針が明示され、同じ流れの中で外来医療についても、データ提出に係る評価を見直す考え方が示されてきました。
その上で、生活習慣病管理料において政策当局が短冊の中でも明確に打ち出しているのが、「生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する」という評価軸です。短冊では、外来データ提出加算について、診療報酬の請求状況や治療管理の状況等の“診療の内容”に関するデータを提出する医療機関のうち、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関を新たに評価することが示されています。
つまり国が求めているのは、単に「取り組んでいる」ことの自己申告ではなく、ガイドラインに沿った診療が実際に行われ、その結果(アウトカムも含めた“実績”)がデータとして継続的に示せる状態です。このため、評価の土台としてまず外来データ提出を継続的かつ適切に行える体制つくりを求め、かつ“質の高い管理の実績”がある医療機関を段階的に高く評価する――という設計思想になっています
3. 病院やクリニックへの影響と求められる対処
①外来データ提出に向けた準備と、継続的に運用できる仕組み・体制づくり
外来データ提出を実施するにあたり、まず最初につまずきやすいのは、「提出そのもの」ではなく、提出できる状態にするための準備です。実務上、必要なデータを記録しながら診療をし、エラーなどをなくし提出できる形式に整え、内容を点検できるようにするまでに、通常でも4〜6か月程度かかります。試行データ作成時にデータ漏れがあったり、不備による差戻し(審査落ち)になれば、最初からやり直す必要があり、準備期間が実質的に倍に伸びるケースも想定しておくべきです。したがって、まず重要なのは「早く始めること」です。
外来データ提出の準備には、国が定める期限が存在します(下図は2025年の例で、2026年も概ね同様のサイクルになる想定)。特に試行データが問題になりやく、実務上、失敗や差戻しリスクを織り込むと、かなりの長期戦になることもあるため、準備開始はできるだけ早く着手しておくことが望まれます。現実的な次の試行データのタイミングと予想される6月、7月に間に合わせるためには、4月くらいから準備を開始する必要があります。
そして、準備が整った後に必要になるのが、提出を継続的に回し続ける運用です。外来データ提出は一度提出して終わりではなく、定期的に「抽出→点検→期限内提出」を繰り返す業務になります。提出が属人化すると継続が難しくなるため、早い段階から、院内の役割分担と、毎回迷わず回せる手順を固定し、日常業務として定着させることが重要です。
■ 試行回毎の届出期限とデータ提出期限(2025年度の場合)
| 対象回 | 様式7の10届出期限 | 試行データ作成対象月 | 試行データ提出期限(オンライン) |
|---|---|---|---|
| 第1回目 | 5月20日 | 6月・7月 | 2025年8月28日(木) 12時00分00秒まで ※配送2025年8月27日(水) |
| 第2回目 | 8月20日 | 9月・10月 | 2025年11月27日(木) 12時00分00秒まで ※配送2025年11月26日(水) |
| 第3回目 | 11月20日 | 12月・1月 | 2026年2月26日(木) 12時00分00秒まで ※配送2026年2月25日(水) |
| 第4回目 | 2月20日 | 2月・ 3月 | 2026年4月23日(木) 12時00分00秒まで ※配送2026年4月22日(水) |
②実績データに結果が適切に表れるような”質の高い診療”を行うための仕組み・体制づくり
外来データ提出は、提出運用ができるようになるだけでは十分ではありません。今回の改定が目指すのは、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を、実際に継続して行い、その結果が“実績データ”に現れる状態にすることです。言い換えると、提出データは単なる事務作業ではなく、診療の質そのものを反映する“鏡”になります。外来データ提出の形式的な準備や運用以上に、この点が医療機関にとって、もっとも本質的な取り組みになります。
そのため医療機関側には、院内として「質の高い管理」を再現性のある仕組みに落とし込むことが求められます。具体的には、(1)ガイドライン準拠の診療プロセス(評価・検査・指導・フォロー)の標準化、(2)各患者にあった、また患者が理解し実行できる生活習慣指導コミニュケーション、(2)患者の生活習慣改善を継続支援する運用を、セットで設計することが必要です。
生活習慣病管理では、具体的な項目・数字に基づく指導(例:食事・運動・体重・血圧・検査値の目標と行動)と、患者の理解度・実行度に合わせた患者に対する個別最適化された細かな指導が実績(アウトカム)に直結しますが、一方でこれらは手間と時間をとられるために、効率化の工夫もあわせて必要になります。
まず院内で決めたいこと。~先に決めるほど楽になります~
① 外来データ提出は、まずなにより"準備を開始"
外来データ提出は、運用設計以前にの4〜6か月以上の準備期間が必要です。そのため、まずは早めに「準備を開始できる状態」を最優先で整える必要があります。当面は、以下から着手するのが有効です。
- 準備の全体像(流れ)を理解する
- 準備スケジュールと体制を決める
- 院内インフラ(システム等)が要件を満たすか、新たな対応が必要かを確認する
② 高い診療の質が、実績データに現れるようにするための準備
質を上げて実績として残す取り組みには、 (1)ガイドライン準拠の診療プロセスの標準化、(2)各患者にあった、また患者が理解し実行できる生活習慣指導コミニュケーション、(2)患者の生活習慣改善を継続支援する運用というものがありますが、そのまま現場に追加すると医師・スタッフの手間が増え、継続できないリスクがあります。質の確保と効率化を両立させる手法を早めに検討していくことが求められます。
- アウトカムにつながる診療の質の高め方の院内の理解を統一する(看護師などとの連携が必要な場合もあります)
- 効率化のための手法を検討・導入する
4. 短冊に示された改定の具体的な内容
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の見直し
-
“包括の範囲”を整理(=必要な医学管理等を別途実施しやすく)
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)の趣旨(生活習慣に関する総合治療管理)を超えて、患者に別途行われるべき医学管理などについて、実施を適切に推進する観点から、包括範囲から除く方向が示されています。
-
糖尿病主病患者の「在宅自己注射指導管理」の扱いを見直し
- 糖尿病を主病とする患者について、糖尿病"以外"の併存疾患に対する在宅自己注射指導管理を推進する観点から、糖尿病適応薬以外の薬剤に係る在宅自己注射指導管理料の算定を可能とする旨が明記されています。
-
眼科・歯科連携の評価を新設(加算を追加)
- 生活習慣病の管理に加えて、眼科・歯科との連携を推進する観点から、紹介等を行った場合の評価(眼科・歯科連携加算 等)を新設する方針が示されています。(※点数は●●表記で未開示)
- 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、要な血液検査等を少なくとも6ヵ月に1回以上は行うことを要件化
- 療養計画書の“署名”を不要化
外来データ提出加算の見直し
-
“質の高い生活習慣病管理”をより高く評価する枠組みを新設(充実管理加算)
- 外来データ提出加算について、ガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、提出データを踏まえた新たな評価の新設と、評価体系の見直しが示されています。
-
具体的に、主病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)毎に充実管理加算1~3の3段階で評価する構成が提示されています。(※点数は●●表記で未開示また、「十分な」「相当の」の定義も未開示)
- 充実管理加算1:体制整備、かつ十分な実績
- 充実管理加算2:体制整備、かつ相当の実績
- 充実管理加算3:体制整備のみ
-
経過措置
- 2026年3月31日時点で、外来データ継続して厚生労働省に提出している場合は(現行の生活習慣病管理料の注4に該当する場合は)、2027年3月31日までは充実管理加算1相当で評価。
- 機能強化加算においても、外来データ提出の届出が望ましいとの記載が加わりました。
本記事は、厚生労働省が公表した短冊の内容をもとに、令和8年度(2026年度)の診療報酬改定における生活習慣病管理料の見直しポイントと、それに伴い病院・クリニックで求められる対応を整理したものです。点数・算定要件の詳細は、今後の通知・疑義解釈等で順次明確化されるため、確定情報が示され次第、本記事も速やかに更新します。
更新履歴
2026.1.23 14:00 短冊公表を受けて記事作成。